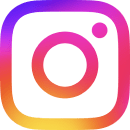⑦子どもに伝わる指示の出し方
こんにちは!いつママの「ゆみ」(保育士歴10年、4歳と5歳年子の母)です!
以前インタビューをさせていただいた、神奈川県平塚市で相談支援専門員として活躍していらっしやる、『相談室つぼみ』の和久井先生に再び!インタビューをさせていただきました!
今回は「子どもに伝わる指示の出し方」について、お話を聞いてきました!
子どもに「お片付けしてね」って言ってもなかなかやってくれなかったり、今「いい子にしてほしい」って思っててもいい子にしてくれなかったり…。そんな時どうしたらいいのか、どうやったらこちらの指示に従ってくれるのか、を詳しくそして分かりやすく教えてもらいました!
1.具体的な指示と褒める
和久井さん:
今まででは子どもの自発的な行動に対するママの対応の仕方でしたが、今度はママが「これやって欲しい」と思うことを子どもにやってもらうにはどうしたらいいかお話します。
ママと子どもがいざこざに発展しないで、子どもにやるべきことをやってもらう方法、つまり子どもに伝わる指示の出し方です。
ママが「こうしてもらいたい」と思うものを指示として子どもに出して、子どもがそれに従うことをお話しますね。
まず「指示」という言葉は、ペアトレの中で言うとコミュニケーションの道具と言われています。
コミュニケーションの道具であり、「〇〇するよ」「〇〇の時間だよ」と、やるべき行動の内容を子どもに伝えます。
この指示は「何やってるの?」「どうして何々なの?」というお説教とは違います。
指示を伝える為には真剣な声と態度が必要です。
子どもにはなぜ指示が大事なのかというと、例えば怒られますよね。「こんなことやっちゃダメでしょ!」って。
子どもは「じゃあ何をやったらいいの?」というところがわからないから、ママがやって欲しいことを伝えるのが大事だと思います。
子どもに伝わる指示を出して、その指示に従ったら子どもを褒めます。
この伝わる指示の仕方と褒めることを繰り返すと、子どもの行動が変わっていくと言われています。
「いい子にして」と言う言葉は抽象的な表現で、子どもはどうしたら「いい子」なのかわかりません。
「いい子にして欲しい」ではなくて、「椅子に座って待ってて」「絵本を読んで待ってて」と具体的な行動を指示するのが大事です。
また「ダメダメ、それやっちゃダメ」よりも「それじゃなくてこれやろうよ」と代わりにやって欲しい行動を伝えるのも大事です。
和久井さん:
ゆみママのお子さん、片付け上手ですか?
ゆみママ:
いいえ。しかも全然してくれないです。(笑)
和久井さん:
お買い物に行かなきゃいけないけど、散らばっている時、ゆみママは何と言いますか?
ゆみママ:
時間を決めて「長い針が12になったら行くから、9になったらお片付けするよ」と予告はするんですが、予告通りに行かないので、「お片付けするよー!」って何回も言ってますね(笑)
和久井さん:
大人は使ったものを片付けるのは当たり前の行動ですが、子どもはミニカーや積み木、本などがいっぱい出ているので、何をしていいかわからなくなっちゃうんですよね。
だから小さなお仕事を指示してあげると考えると楽なんです。
「本は本箱に入れてね」「ミニカーはこの箱に入れようね」「おままごとはここに入れようね」と、お片付けを一括りにせず、小さなお仕事としてやっていくと良いと思います。
ゆみママ:
「じゃあちょっとお仕事お願いね!」って声をかけるといいんですね♪
和久井さん:
そうなんです!「長い針が10になったらお買い物行くから、9になったらみんなにお仕事言うから聞いてね」と言ってあげるといいんです。
ゆみママ:
確かにそれを言うと、「お仕事?お片付けやろうかな?」っていう気持ちが出てくるかもしれませんね!
和久井さん:
でも何度も使えるわけじゃないんですけどね(笑)
2.感情的にならずに…
感情的な指示の出し方は感情しか子どもには伝わらず、子どもは何をすべきか、何がしちゃいけないのかがわからなくなります。
そこは冷静な態度でやりましょう。
3.指示とお願い
指示とお願いを間違えやすいです。
「お願いだからこれ片付けて」と言うママもいます。
お願いは、語源を見ていくと…人に協力をしてもらって感謝するという意味なのですが、発達に課題のある子どもたちは人の気持ちに沿って動くのが難しいです。
「お願いだから手伝って」と言うと、本来なら「あんたの仕事でしょ」と思うけど、感情が入るから「この人困ってるんだ」と思って手伝ってあげようかなと思うのが俗にいうお願いです。
人に協力して感謝されるということです。
でも子どもは自分で出したものなんだから、自分が片付けるのは当たり前です。
そこはお願いじゃないですよね。
お片付けっていう言葉だと何をどうすればいいかわからないので、細かく伝えてあげましょう。
「おもちゃをおもちゃ箱にしまってくれるかな?」は、子どもは「しまわなくてもいいのかな?」と決定的な言葉ではないので、「おもちゃをしまってね」とやるべきことはきっぱりと言うのが望ましいです。
4.効果的な指示の出し方のポイント
和久井さん:
ペアトレの中で効果的な指示の出し方があります。
①まずは子どもの注意を引きます。
子どもがリビングで遊んでいて、ママはキッチンにいる場合、キッチンのほうから大きい声で「お片付けしてね」と言っても、子どもは遊びに夢中なので聞いていないことが多いです。
まず子どもの注意を引くことから始めましょう。
「お片付けしようね、本を本箱にしまおうね」と、子どもにも分かるように「今からママが伝えるよ」と伝わるように目と目を合わせて伝える。
②そして短く具体的に伝える。
③感情的にならず落ち着いてきっぱりと「本を本箱にしまいましょう」と言う。
どんなに小さなことでも子どもが従おうとした時は、すぐに褒めるのが大事です。
例えば「本を本箱にしまってね」と言ったら「はい」と返事したり、立ち上がったりした時は褒める。
よくママが言いがちなのは、「本を本箱にしまってね」と指示し、子どもが従ったら「ママできたよ!」と言う、ママは「ありがとう。上手だったね」と褒めるが、「でも昨日も言ったよね?全然動かなかったでしょう?いつもこうして動いてくれるとママ助かるんだけど、これからもママが言ったらそうやって動いてくれる?」って言いがちじゃないですか。
これだと子どもは褒められたのか注意されたのか分からなくなる。
だからやっぱり褒める時はしっかり褒めるべきなんですね。
5.CCQとは?
和久井さん:
ペアトレでは、指示を出す時のコツとしてCCQがあります。
Calm Close Quitet
Cは感情的にならず穏やかに、Cは子どもに近づいて、Qは声のトーンを抑えて静かに。
感情的にならないで気持ちの良い状態で指示を出すのがすごく大事ですよ。
ゆみママ:
家事をしているとなかなか近づいて声をかけるというのは、省いちゃうことが多いので、近づいて声をかけた時とそうでない時では、やっぱり入り方が違うなって思いますね。
和久井さん:
そうですよね~。
子どもに近づく時っていうは、怒る時や注意したい時が多いと思うんですよね。
良いことをした時にも近寄って褒めてほしいなって思うんです。
大変なんですけどね(笑)
ゆみママ:
子どもはそっちの方が嬉しいですよね。
ママが近寄ってきてくれて、褒めてくれるんですものね。
和久井さん:
指示は1回で従うとは限らないので、子どもが従うまで3~4回繰り返すのも大事です。
何回かやってる内に子どもが指示に従ったら、従おうとしたらすぐに褒めるもの大事です。
いきなり「お片付けね!」と言うよりも、指示を出す前に予告をするのも大事。
例えば「10になったら片付け」と指示するなら、9の時点で「あと10分したら片付けだよ」と伝える。
予告は、今している行動をもうすぐやめて、次の行動に移らなければならない行動を予め伝えてあげるというのが予告です。
予告の凄く良いところは、「あと5分したらお片付けだよ」「あと3回やったら終わりだよ」と、子どもが今のこの楽しい時間をあと5分間楽しめる猶予を与えてくれる。
予告をすることで子どもは切り替える準備ができるから、今やっている行動が次に移りやすくなると言われています。
子どもが予告に従ったらしっかりと褒めてあげてくださいね。
もう1つが…選択を与えること。
選択とは2つ以上の可能性のあるやり方を提案し、その内一つを選ばせること。
選択の良い所は、子どもが自分の意志で選んでやるので気持ちよく従うことができます。
「こっちにする?」と言った時に、子どもがそれをしなかった、選ばなかった時…「これはあなた(子ども)が選んだことだから、最後までやらなきゃだめだよ」と言える。
ママが選んでしまったら子どもは「だってこれはママが選んだんじゃん」と言われちゃったら何もいえなくなっちゃうからね。(笑)
例えば…ママが「今日のお洋服赤いTシャツと黄色いTシャツのどっち着る?」って選択を与えた時に、子どもは「赤いTシャツにする!」って選んでくれればいいけれど、「どっちも嫌だ!」って言った時にママが「じゃあもう一回聞くね?どっちがいい?」と言ったけどそれでも嫌だとなったら、ママは「もうしょうがないわね…どれがいいの?」って言いがちだと思うんです。
そしたらもう最初から選択をさせないで子どもに好きなお洋服を選ばせることが大事です。
今日は発表会があるから、選ばなきゃいけない…そういう時に「嫌だ嫌だ!僕はこっちがいい!」って言っても、どっちかしか選べない時は、ママが「じゃあ分かった!代わりにママが選ぶから、それでもいい?」って言う。そこも選択させてあげる。
子どもも「ママが選ぶんだったらいいよ、僕が選ぶから!」って言うかもしれないし。(笑)
なので、「だったら好きなの選んでね。」って言うんだったら、最初から選択をさせない。
と言うのが大事になります。
あと一つ…「〇〇したら〇〇できる」っていう取り決めを一つ作ってあげると良いかと思います。
行動あるいは課題をする代わりに、何か子どもに特典をあげる。
でもこの特典って言うのは、特別なところに行くとか特別な物を用意してあげるとかじゃなく、子どもが好きで親が簡単に与えることができる物だと良いと思います。
例えば…ママが夜にお友だちとの飲み会の予定がある。子ども達を早めにお風呂に入れて、パパが帰って来るまでに着替えさせておかないと、出発できないってなったとします。
いつもだったらお風呂の時間は19時なんだけど、ママが「今日はママに御用があるから18時にお風呂に入ろうね!」と子ども言ったら「嫌だ!」って言われたら、「18時にお風呂に入って、お風呂から出たら今日はアイス食べていいよ!」ってママが言うんですね。
そしたら子ども達は「え!入る入る!」ってなりますよね。(笑)
こんな感じの取り決めになりますね。
よくママ達は「お片付けできなかったら、おやつあげないよ!」とか「〇〇出来なかったら〇〇ダメだよ」って否定形・否定形で言うことが多いと思うんですね。
でもそれって子どもにとっては物凄く何もやりたくなくなるくらい嫌な事なんですよね。楽しくないから。
子どもが楽しくママの指示に従ってもらうためには肯定系・肯定系でしていくと良いんです。
ゆみママ:
私もついつい、「ほら!〇〇しないと〇〇できなくなっちゃうよ!」って言っちゃうことがあります。(汗)
なるべく意識して「〇〇したら〇〇できるよ!」って言い換えようと思うのに、ついポロっと言っちゃう事があります。(笑)
和久井さん:
これ(肯定的な言葉)を意識するだけでも違うのかなって思います♪
ゆみママ:
ありがとうございました!
今回もとても濃い内容でしたね。
具体的な指示を出すことで、子どもに指示が伝わる方法や肯定的な言葉で、ママも子どもも楽しくそして気持ちよく関わることができるのはとてもいいなと思いました。
次回でインタビュー記事が最後となります!
この記事に辿り着いてくださった方へ、今日も一日お疲れさまです★
いつママのInstagramでは、保育士ママならではの知恵が盛りだくさん!こちらもみてね!
いつママのInstagram 『相談室つぼみ』和久井さんへの質問やご相談はこちらから♪
『相談室つぼみ』和久井さんへの質問やご相談はこちらから♪
お気軽にご相談ください♪