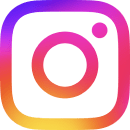③子どもの行動を3つに分ける
こんにちは!いつママの「ゆみ」(保育士歴10年、4歳と5歳年子の母)です!
以前インタビューをさせていただいた、神奈川県平塚市で相談支援専門員として活躍していらっしやる、『相談室つぼみ』の和久井先生に再び!インタビューをさせていただきました!
今回は「子どもの行動を3つに分ける」という内容になっています!
子どもの行動を3つに分けるってどういうこと?ってハテナだらけだったのですが…、聞いていくうちに「なるほど!」「こんな時はこうするのか!」と思える内容でした!
子どもの行動を3つに分けた時…

ペアトレは、行動を3つに分けましょうと言われています。
前回のインタビューでも少しお話したのですが…
「行動を3つに分けましょう」からスタートします。
行動を3つに分けた時
「好ましい行動」「好ましくない行動」「危険許しがたい行動」に分かれます。
①「好ましい行動」の時は「褒める」
褒めるって大事なんだよというお話です。
注目のパワーとも言うんです。
②「好ましくない行動」に対しては、上手な無視をしましょう。
「褒める」ことと「無視」を組み合わせて、子どもの行動を変えていきましょう。
次に効果的な指示を出しましょう。
どういう風に指示を出したら、ママが思うような行動を子どもが取ってくれるのか…という効果的な指示の出し方。
③「危険許しがたい行動」の時には、警告とペナルティを与える。
このような順番になっています。
なのでこの順番に沿ってお話をさせていただきますね!
和久井さん:
子どもの行動を3つに分けましょう。
1つ目は好ましい行動、2つ目は好ましくない行動、3つ目は危険・許しがたい行動です。
表にすると分かりやすいですが、言葉で説明するのは難しいので、分からなければ後で質問してください。
好ましい行動とは、ママにとってこの行動大好き!嬉しい!と思えることが好ましい行動です。
例えば、「行ってきます」と元気よく言ってくれること。これって凄く良いですよね!
きっとママ達も「いつも元気な声で嬉しいよ」って毎回毎回褒めるってことはなくて、当たり前のように感じてしまっているかもしれないんですが、毎日褒めることは減ってしまうかもしれませんが、毎回褒めてあげましょう。
好ましい行動が起きた時はすぐに褒めてください。
「この子は褒められるような行動をしない」と言うお母さんもいます。
褒めれらるような行動を取らないから、褒められない。
当たり前かもしれないけど、今できていて、止めて欲しくない行動も好ましい行動の一つになるんです。
「その声聞くとママも元気が出る」「元気に行ける(保育園)ことがママも凄く嬉しいよ♪」と何でもいいので伝えるのも良いと思います。
2番目は好ましくない行動です。
これはママがこういう行動はとって欲しくない、これは嫌いな行動だな、できれば減らしたい行動だな、と思うのが好ましくない行動です。
これはいつもだったら、ママは注意しちゃうじゃないですか。
「ダメよ」「やらないでね」とか。
でもぺアトレはそこのところを無視、行動を無視するんですよ。
お子さんを無視しちゃったら虐待になってしまうので、行動だけを無視します。
そこが今までにないやり方なのかなって。
今までは褒めるか叱るかどっちかだったと思うんですけれども、そこに無視をするっていうのを加えていただけると良いのかなって思います。
具体的な無視の仕方は後ほどお伝えしますね。
3番目が危険・許しがたい行動です。
これはどんなのかっていうと、人や物を傷つけるような行動、ママが絶対ダメだと思うような行動、いくら注意してもやめない執拗な行動、とにかく今やめさせたい行動です。
例えば、お友達に物を投げるとか、道路でママの手をパッと離すとか。
そういう時はすぐに制限を設け、介入しなきゃいけないのが危険許しがたい行動です。
なのでまとめると、好ましい行動は褒める。
ママがこの行動大好き!ずっとやって欲しいなと思う行動は褒める。
好ましくない行動は今減らしてもらいたい行動、これは無視をする。
危険許しがたい行動は、人や物を傷つけたり、いくら注意してもやめない時はすぐに制限を設けたり、介入してやめさせる。
この3つに分けます。
何となく分かりました?
ゆみママ:
分かりました。
今までは2パターンだったのが、3つ目の危険許しがたい行動をすぐ止めてやめさせるって、なかなか止められない子もいるから難しいところですが、大事だなって思いました。
和久井さん:
制限を設ける、無視をするっていうのはどういうような形でやっていったら良いのかっていうのもお話をしていきたいなって思います。
危険・許しがたい行動

和久井さん:
ペアレンツトレーニング、行動を3つに分けましたよね。
好ましい行動はこれはいっぱい褒めてあげましょう。肯定的な注目をしましょう。
好ましくない行動、これは無視しましょう。
そして最後に危険・許しがたい行動、今日はそこをお伝えできたらと思います。
和久井さん:
危険・許しがたい行動は、褒めたり、無視したりしても行動が減らない時に、制限を設けましょう。
制限を設けるのは、お子さんの行動をママがコントロールしたり、ルールを守らせるのに役立ちます。
制限を設ける方法として、イエローカードがあります。
サッカーとかでもあると思うんですけど…もし子どもがある行動を始めたり、やめたりしない時に当然与えられる結果を宣言することなんです。
レッドカードはすぐに退場だけど、イエローカードは今度やったらだめですよっていう意味なんですね。
例えば、兄弟で仲良くブロックで遊んでいて、いつの間にか投げ合いになり、弟が泣き出したとします。
ママが「ブロックはここで遊ばなきゃいけないものでしょ。今度投げたら、10分間遊んじゃいけないよ」と言うように、今度同じことをしたら与えられる罰(ペナルティ)を宣言します。
罰は子どもにとって一番身近なもの、例えば「ブロックを10分間使っちゃいけない」が良いですね。
「もうずっと使わせない!」っていうのは無理な話なので。
お母さんによくあるのは「喧嘩ばっかりするんだったら、今度の日曜日にディズニーランド行かないからね」ですが、計画を立ててチケットも買っているなら、行かないということはないですよね。
家族で楽しむことなので。
だからママの言葉は単なる脅しになっちゃうから、その時は「サラッと流せばいっか~」って子どもに流されちゃう。
身近にあるもので子どもが取られたら嫌がるものを選ぶのが良いと思います。
効果的なイエローカードの出し方は、やめてほしい行動と従うべき行動を伝えることです。
「ブロックは投げないで遊ぶんだよ」と子ども達が取るべき行動を伝えるんです。
もし従わなかった時のペナルティを具体的に伝える。
「10分間使っちゃいけないよ」と。
で、このイエローカードは1回だけ使います。
何回もやると意味がなくなります。
警告っていうのは子どもが指示に従える最後のチャンスです。
ママが「ブロックは投げちゃいけないよ」と言って、子どもたちが「うん」と言ってちゃんと遊べていたらそこはしっかりと褒めてあげましょう。
和久井さん:
「ママの言うこと聞いてくれてありがとう。仲良く遊ぶと気持ちいいね」と。
もし警告に従わなかったら、今度はイエローカードではなくて罰(ペナルティ)を与えます。
当然与えられる罰をちゃんと言う。
ママがイエローカードとしていったにもかかわらず、またブロックを投げていたら…
「ねえねえ、さっきママ言ったよね。今度やったら10分間ブロック使っちゃいけないよって。だから遊ぶのをやめます!」と言って、タイマーをかける。ママが「10分間そこに座っててね」と伝えて。
正座とかじゃなくていいんです。
楽しいことを与えないようにします。
罰(ペナルティ)は子どもがお約束を果たさなかった結果として、何か大事なものを失うことです。
さっきも言ったように難しいことをするのではなく身近にあるもので、子どもにとって興味のあることで、大事なもので、親がコントロールできるものが良いですね。
そして心置きなく取り上げられるもの…ですね。(笑)
罰(ペナルティ)の期間は1日ではなく、10分などの短い時間でやるのが良いです。
罰(ペナルティ)は問題行動と結びついているものが一番いいのかなって思います。
(ブロックを投げてるから、ブロックでは遊べない…など)
お尻ペンペンなどの体罰は絶対しないでください。
和久井さん:
ペナルティはお説教ではないんですよね。
子どもが選択した結果、「もう投げないで遊んでね」「投げたら遊べないよ」って言ったにもかかわらず投げたから、子どもが自らそれを選択したわけです。
イエローカードは親にとっても子どもにして欲しいことを伝える最後のチャンスなんですよね。
警告(イエローカード)の段階で従えられたら、必ず褒めてください。
警告の前にワンクッション置いて「上手に遊べたら、おやつ食べようね」などと言うのも良いでしょう。
ペナルティの時間が終わったら、「何度も言うけどこんなことしちゃだめよ?」ってお説教はせず、水に流します。
ペナルティの後にすぐ同じことをした時は、警告を繰り返さず、すぐに罰(ペナルティ)を与えます。
「はい、さっき言ったよね」ってすぐに罰(ペナルティ)を与えると良いと思います。
和久井さん:
〇好ましい行動の時は褒める。
〇好ましくない行動や許しがたい行動の時は、無視をしたり介入したりして、行動をやめたら褒める。
褒めたり指示しても改善しなくなれば、イエローカードを出す。
イエローカードにも従わない時は、罰(ペナルティ)を与える。
いきなり罰を与えるのではなく、まずは褒めて、無視して、介入して、警告をして、それでもダメだった時に罰を与えるという段階があります。
例えば小学生ぐらいだったら、愛の鐘が鳴ったらおうちに帰んなきゃダメだよって言ってるのになかなか守らないっていう子いた時に…
そういう時は家族会議がすごく効果があるんですよ。
家族会議はパパもママも、お姉ちゃんやお兄ちゃん、妹とかみんなで会議をする。
会議と言っても10分とか15分ぐらいみんなに集まってもらうんです。
「〇〇ちゃん、ママが約束しても守ってくれないんだけど、どうしたらいいと思う?」ってみんなに考えさせるんです。
ペアレントトレーニングでも、罰(ペナルティ)の与え方が難しい時に、罰を与えるんじゃなくてみんなで考えるのも1つの方法として家族会議があるんです。
ある家族会議をやったお姉ちゃんが、小学校2年生の妹が約束を守らないことに対して「私だって遊びたいけど、暗くなると変な人が来るから、決められた時間に帰らないといけない。みんなが守ってるから守らないといけない」と言ったら、妹はそれから時間を守るようになったんです。
ゆみママ:
親からの言葉より兄弟からの言葉の方が響くことがありますよね!
和久井さん:
うんうん!ありますよね!!
ゆみママ:
下の子が今よりちっちゃい時に、お兄ちゃんの声掛けだったら聞くっていうことがありました(笑)
お兄ちゃんのことが大好きだから、お兄ちゃんの言うことだったら聞くっていう感じで。
やっぱり響くものがあるんですかね~。
和久井さん:
あるんでしょうね~!
ちっちゃい子だったら分からないかもしれないんですが、大きくなったらこういう家族会議も良いかもしれないですよね!
タイムアウト

和久井さん:
あともう1つタイムアウトというものがあるんですね。
これは先ほどの10分間ブロックできないよっていうものと同じなんですが…。
楽しいことや刺激を一切去ることです。楽しい遊びに参加できないということです。
これはすごく使いやすいです。
「ママの話が聞けなかったらイエローカードを出して、今度こうだったらここに10分間座ってるんだよ」というのは効果があります。
ただ、おじいちゃんおばあちゃんと同居している場合は、お姑さんが「かわいそうなことやめなさい」とか「もう分かるんだから」と言うことがあるので、おじいちゃんおばあちゃんにも「今からタイムアウトをするから、声かけしないでね」と伝えておく必要があります。
これはティーチャーズトレーニングでも使われていて、保育園や学校の先生たちも、タイムアウトしている子に声かけしないように他の先生に伝えています。
いたずらっ子がじっと座っていると「どうしたの?今日は大人しいじゃん」と声かけたくなるんだけど、声はかけずにそこはみんなで取り組んでやるといいと思います。
ペアレントトレーニングには色々な方法があって、一度には全部できないかもしれないんですけど…
「こんなやり方があったんだ」「こういうのやってみようかな」と思えるだけでもいいんです。
ママが元気な時にやるのがいいと思います。
ゆみママ:
無理なく進めていけばいいんですよね。その時々で。
和久井さん:
それが一番だと思います!
つたない話でしたが、分からないことがあったらいつでも聞いてください。
ゆみママ:
ありがとうございました!
子どもの行動を3つに分ける…とても興味深い内容でした!やって欲しくない時にはどのように対処すればいいのかも詳しくお話していただけたので、私も実践してみようと思います!!!
この記事に辿り着いてくださった方へ、今日も一日お疲れさまです★
いつママのInstagramでは、保育士ママならではの知恵が盛りだくさん!こちらもみてね!
いつママのInstagram 『相談室つぼみ』和久井さんへの質問やご相談はこちらから♪
『相談室つぼみ』和久井さんへの質問やご相談はこちらから♪
お気軽にご相談ください♪